電力会社と契約する際、「契約アンペア数」というものがあります。この数値はなんとなく決めている人は以上に多いです(というか、ほとんどの人はテキトーに決めています)。
しかし、テキトーに決めることで日常生活で困ることが出てくることもありますので、この記事では、何に注意していく必要があるかを徹底解説します。
そして、最適なアンペア数はいくつなのかをズバリご紹介いたします(そこだけが知りたい方は目次から飛んでください)。
これから契約する方も、既に契約済みの方も参考になる情報ですので、これを機に一度契約アンペア数を見直すと良いでしょう!
契約アンペア数とは
契約アンペア数というのは、家庭で使用できる電流の最大量のことです。基本的に、契約アンペア数が多ければ多いほど電気料金は高くなりますが、その分同時に多くの家電を使うことができます。
参考:「アンペア」はどこで使われる?
- 日常生活: 家庭用電化製品の消費電力を表す際にアンペアが使われます。例えば、20アンペアのブレーカーは、同時に使用する家電製品の合計電流が20アンペアを超えると、回路を遮断します。
- 電子回路: 電子回路の設計や分析において、アンペアは非常に重要な役割を果たします。電子部品の定格電流を超えないようにすることが必要です。
アンペアは、電流の流れの強さを測定する基本的な単位です。電気回路において電流の強さを管理することは、安全性や機器の正常な動作を維持するために非常に重要です。アンペアの概念を理解することで、電気の使用や電子機器の設計に役立てることができます。
参考:電流計算の基本
電流(I)は、電圧(V)と抵抗(R)の関係を表すオームの法則を使って V=RIで計算できます。
ここで、I はアンペアで表される電流、V はボルトで表される電圧、R はオームで表される抵抗です。
最適な契約アンペア数の決め方
家庭やオフィスで電力契約のアンペア数を決めることは、日常の電力使用量に応じて適切な電力供給を確保するために非常に重要です。
契約アンペア数が適切でないと、ブレーカーが頻繁に落ちたり、逆に無駄な電力費用がかかることがあります。
以下に、最適な契約アンペア数を決めるための基本的な手順を説明します。
1. 各家電のアンペア数を把握する
まずは、各家電がどのくらい電流を使用しているかを把握しておきましょう。
| エアコン | 6.6A |
| 電気カーペット | 8A |
| テレビ | 2.1A |
| 掃除機 | 10A |
| アイロン | 14A |
| ヘアードライヤー | 12A |
| 冷蔵庫 | 2.5A |
| 電子レンジ | 15A |
| 炊飯器 | 13A |
| IHクッキングヒーター | 30A |
| 食器洗い乾燥機 | 13A |
| ドラム式洗濯乾燥機 | 13A |
上の表をご覧の通り、電化製品はかなり多くの電流を使用します。そのため、例えば、エアコンとドライヤーを同時に使うと合計で18.6Aとなり、契約アンペア数15Aであればブレーカーが落ちてしまいます。
2. 同時使用の想定
次に、同時に使用する電気機器の数を考えます。例えば、エアコン、冷蔵庫、照明、テレビを同時に使うことが多い場合、それらの合計アンペア数を計算します。
その上で、契約アンペア数を決めていきましょう。
4. 余裕を持って契約アンペア数を決定
突発的な電力使用増加にも対応できるよう、余裕を持って契約アンペア数を決定しましょう。
例えば、最大の合計アンペア数が30Aの場合、40Aの契約にしておきましょう。
最後は、電力会社に相談して、最適な契約アンペア数を決定します。多くの電力会社は、10A、20A、30A、40A、50A、60Aなどの段階で契約を提供しています。
自分の生活スタイルや使用パターンに合ったアンペア数を選びましょう。
ズバリ!最適な契約アンペア数は?
1人暮らしの場合は30A、家族がいる場合は40A~60Aを目安にすると良いでしょう。
電流を多く使う電化製品(電子レンジ、電気ケトル、ドライヤー等)をあまり使わない場合は、目安よりも低いアンペア数でも問題ありません。
契約アンペアが「多い or 少ない」とどうなる?
契約アンペア数が多いと電気代が高くなる
基本的に、電力会社は契約アンペア数が高くなるにつれて基本料金を高く設定しています。
以下に、目安ですが契約アンペアと基本料金の関係をまとめておきます。
| 契約アンペア | 基本料金(月額、税込) |
|---|---|
| 10A | 280.8円 |
| 15A | 421.2円 |
| 20A | 561.6円 |
| 30A | 842.4円 |
| 40A | 1,123.2円 |
| 50A | 1,404円 |
| 60A | 1,684.8円 |
契約アンペア数が少ないとブレーカーがすぐに落ちる
契約アンペア数が少ないと、家電を2~3個使っただけでブレーカーが落ちるということになります。
家電をほとんど使わないという方はそれでも大丈夫ですが、多くの方は家電を使うため、少なくとも30A以上に設定しておくことをおすすめします。
契約アンペア数の変更方法
既に電力会社と契約済みの方で「電気代が高いから契約アンペア数を下げたい!」「ブレーカーがすぐに落ちて困っているから契約アンペア数を上げたい!」という方もいるかと思います。
ここでは、契約アンペア数の変更方法について紹介しておこうと思います。
1. 現状の確認
まず、現在の契約アンペア数と実際の電力使用量を確認します。これにより、現在の契約が適切であるかどうかを判断できます。以下の手順を参考にしてください:
- 電気使用量の確認: 最近の電気料金明細を確認し、月々の使用電力量を把握します。
- 電気機器のリストアップ: 家庭で使用している主要な電気機器とその消費電力をリストアップします。
- 必要なアンペア数の計算: 同時に使用する電気機器の合計アンペア数を計算します。
3. 電力会社への連絡
契約アンペア数の変更を希望する場合は、契約している電力会社に連絡を取ります。一般的な手順は次の通りです
- カスタマーサポートに連絡: 電力会社のカスタマーサポートセンターに電話やウェブサイトを通じて連絡します。連絡先は電気料金明細や電力会社の公式ウェブサイトに記載されています。
- 契約内容の確認: 現在の契約アンペア数と変更希望のアンペア数を伝えます。変更手続きに必要な情報を確認します。
4. 工事の実施
契約アンペア数の変更には、電力会社の技術者による工事が必要です。以下の点を理解しておきましょう。
- 作業日程の調整: 電力会社と作業日程を調整します。作業には、通常1〜2時間程度かかります。
- 立ち合い: 作業当日は、電力会社の技術者がブレーカーや電力計の設定を変更するため、立ち会いが必要です。
- ブレーカーの交換または設定変更: 必要に応じてブレーカーの交換や設定変更を行います。
- 電力計の調整: 電力計が契約アンペア数に対応するように調整します。
6. 新しい契約内容の確認
作業が完了したら、電力会社から新しい契約内容の確認書類が届きます。以下の点を確認してください。
- 契約アンペア数: 希望通りのアンペア数に変更されていることを確認します。
- 料金プラン: 新しい契約アンペア数に基づく基本料金や使用料金を確認します。
簡単に電気代を節約する方法を紹介!
1.電力会社を乗り換える
2016年4月1日以降、電力会社は自由化しており、消費者は自由に電力会社を選ぶことができるようになっています。
そのため電気代が高いと感じている方は、今の電力会社を無理に使い続ける必要はないのです。
そもそも電気料金の安い電力会社に乗り換えてしまえば、電力使用量は今まで通りでも大幅な節約が可能です。
電力会社を選ぶ上でのポイントを以下にまとめておきます。
・料金を比較する ・ライフスタイルに合った料金プランを選ぶ(日中は仕事の場合は夜間が安くなるプラン等)
・世帯人数から契約アンペア数を決める(1人暮らしなら30Aで十分)
・優良企業であるか確認する
・自分に合った支払方法ができるか確認する
また、電力会社を乗り換える場合、電力会社比較の専用サイトから申し込むことでかなりお得に乗り換えることができます。
一番おすすめの専用サイトはエネチェンジです。
直接電力会社に問い合わせをするとキャッシュバックなどは無いことが多いですが、エネチェンジから申し込みをすると、多いと「年間で3万円キャッシュバック」など大きなメリットが得られます。
2.契約プランを変更する
多くの電力会社では契約プランを複数の中から選択することができます。最もスタンダードな契約プランは「従量電灯」というプランであり、使用電力量によって電気料金が加算されるプランです。
ただ、割引が適用されるプランに変更することで安くなる場合があります。
例えば、「日中は仕事で家におらず電気をほとんど使わないが、夜はたくさん使う」という場合、夜間の電気料金が割引になるプランにすることでお得に電気を使用することが可能です。
その他にも、基本料金0円で使った分だけ支払うプランや、オール電化向けのプランなど様々なプランを提供している電力会社が多いです。
そのため、自分のライフスタイルに合った契約プランを選ぶことをオススメします。
3.電気料金の支払い方法を見直す
電気料金の支払いをクレジットカードにすることで、ポイント還元を受けることができます。
また電力会社にもよりますが、電気料金の支払いを口座振替にすることで割引が適用されるケースもあります。
契約時になんとなく支払い方法を決めてしまった方は、今一度支払い方法を見直してみると良いでしょう。
4.電気代が高くなる時間帯の使用を抑える
従量電灯などスタンダードな契約プランにしている方は時間帯による電気料金の違いはありませんが、プランによっては、時間帯による電気料金の違いがあります。
電気代が高くなる時間帯を意図的に避け、安くなる時間帯にまとめて使用することで電気代節約につながります。
例えば、昼間の電気料金が安くなるプランの場合、夜に洗濯機などを動かすのは避け、昼間にまとめて動かすほうが節約になるでしょう。
5.省エネ家電に変える
家電全般に言えることですが、メーカーや年式によって消費電力は様々であり、消費電力の大きな家電を使っていると余分な電力を使うため電気代も高くなります。
特に、10年以上まえの冷蔵庫など、古い家電を使っている場合は要注意です。かなり損している可能性が高いです。その場合、最新の冷蔵庫に変えるだけで、年間で5,000~7,000円程度節約することができます。
「でも冷蔵庫を買う値段の方が高くつくんじゃないの?」という声もあるかと思います。
もちろん初期投資は決して安くないですが、長い目で見るとお得になることが多いです。また、最新のものに変更することで冷蔵機能もアップするため、一石二鳥と捉えることができます。
1人暮らしの場合であれば2万円程度で冷蔵庫が買えるため、年間7,000円節約できたとすると、3年でもとがとれることになります。
古い家電を使い続けている場合は思い切って買い変えてみましょう。
古い家電でなくても、いわゆる「省エネ家電」に買い替えることで電気代節約につながることが多いです。
買い替える際は、「消費電力」が今の家電よりも小さいことを必ず確認するようにしましょう。
6.自家発電する
自家発電とは、発電会社から供給される電力を使うのではなく、何らかの発電設備を用いて消費者自らが発電を行うことです。
自家発電すれば、電気を自ら生み出してそれを使うだけなので、電気代を大幅に減少させることができます。
また、自給自足でのエネルギー調達をしているため、再生可能エネルギー発電促進賦課金を抑えることができます。そして、環境問題への貢献にもなります。
さらに、自分で電気を作り出しているため、災害時の停電の心配がありません。非常用電源としても、自家発電は現在注目を集めています。
自家発電して余った電気に関しては、電力会社に売ることもできます。そう考えたら、初期の導入コストはかかるものの長期的に見ると大きな節約につながる可能性が高いです。
自家発電ってどうやれば良い?
自家発電の具体的なやり方ですが、「太陽光発電&蓄電池設置」がおすすめです。太陽光発電であれば、晴れている日であれば、ソーラーパネルが勝手に発電してくれます。
ソーラーパネルと聞くと「なんだか大きそう」とイメージされるかもしれませんが、持ち運びできる小さなものもあります。
太陽光発電をするのであれば、まずは太陽光発電の一括見積もりサービス【エコ発】などで見積をとりましょう。
蓄電池であれば、蓄電池の一括見積もりサービス【エコ発蓄電池】で見積もりをとれば間違いないです。
7.エアコン使用時なるべく外気温度に近い設定温度にする
夏はとくに冷房を長時間つかうと思いますが、その際、なるべく高い温度に設定するようにしましょう。もちろん、涼しいと感じないと意味はないですが、涼しいと感じるギリギリまでは温度を上げると電気代の節約につながります。
冷房の設定温度と外気温度との差が大きければ大きいほど電力使用量は大きくなり、その分電気代も上がってしまいます。そのため、できる限り外気温度に近い温度で冷房を使用しましょう。
ちなみに、外気温度が31℃のときに冷房の設定温度を27℃→28℃に変更するだけで、年間約940円の電気代節約になります。
ただ、無理に温度を上げて体調が悪くなってしまっては意味がないため、無理のない範囲で設定温度を調節するようにしましょう!
暖房使用時も冷房と同様で、外気温度に近い方が節約になります。
外気温度が6℃のときに暖房の設定温度を21℃→20℃に変更するだけで、年間約1,650円の電気代節約になります。
冬場は寒いため、設定温度を上げたくなる気持ちは分かりますが、目的は室内を十分に暖めることなので、室内が暖まっているならむやみに温度を上げないようにしましょう。
室内が十分に暖まってる状態であれば、設定温度を1℃変えたくらいで室内の温度はそこまで変わりません。
※出典:経済産業省 資源エネルギー庁 無理のない省エネ節約
8.断熱シートを活用する
窓に断熱シートを貼ることで、エアコンなどの電気代がかかる家電の使用時間を抑えることができます。
断熱シートは安くで手に入るため、一度検討してみると良いでしょう。
9.室外機の周りにものを置かない
室外機の近くにものを置いている場合、冷暖房の効果が弱まってしまいます。少し離れた場所に移動させるなどして、吹出し口を塞がないように注意しましょう。
10.サーキュレーターを活用する
サーキュレーターはとにかく電気代が安いです。1日8時間で1か月使用しても約180円です。
一方で、エアコンだと1日8時間で1か月使用すると、約13,000円かかってしまいます。
私自身、夏の暑い日にサーキュレーターを活用するようにしているため、大幅に電気代をカットできています。
サーキュレーターだけだと暑いと感じる場合、エアコンとサーキュレーターを併用することをおすすめします。サーキュレーターが室内の空気を素早く循環させてくれるため、エアコンの使用時間が減るはずです。
11.冷蔵庫内のものは壁から離す
冷蔵庫内のものと壁を離さないと、放熱の効率が悪くなり、余分な電力を使うことになります。
冷蔵庫内のものの上と両側が壁に接している状態から片側のみ接している状態に改善するだけで、年間約1,400円の節約になります。
※出典:経済産業省 資源エネルギー庁 無理のない省エネ節約
12.電球形LEDランプを使用する
電球交換をどうせするのであれば「電球形LEDランプ」にすることをおすすめします。明るく、寿命も長くありながら、電球形蛍光灯よりさらに消費電力が小さいのです。
白熱電球を使用している場合、電球形LEDランプに変更することで、年間約2,790円の節約になります(54W→9Wに変更した場合)。
※出典:経済産業省 資源エネルギー庁 無理のない省エネ節約
まとめ
今回は「契約アンペア数」について解説してきました。
結論、契約アンペア数を高くすれば電気代が高くなるし、低くすればブレーカーが落ちやすくなります。
今のライフスタイルを見直し、最適なアンペア数を選ぶことが大切となります。
「契約アンペア数は下げたくないけど、電気代は節約したい!」という方もいるかと思います。
以下で電気代の節約術をたっぷりと50選紹介していますので、ぜひご覧ください!


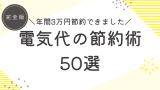


コメント