「電気・ガス・水道代が高い!」「節約したいが方法が分からない」という方は多いです。
生活費において、光熱費が占める割合は大きいです。そのため、「光熱費の節約方法」を知ることは大切です。
そこで、普段から光熱費を安くするために色々試したり、調べまくっている私が、光熱費の節約術15選を紹介します。
実際に私自身、光熱費が高すぎてうんざりしていましが、これから紹介する節約術を実践することで年間7万円の光熱費節約を達成しました。そのため、最近は生活費に余裕ができ、気持ち的に楽になりました。
皆さんも光熱費節約節約を通して今よりも余裕のある生活を実現していきましょう!
電気代・ガス代・水道代が高い原因についてもそれぞれ解説しているため、まずは「自分は何が原因で電気代・ガス代・水道代が高くなっているのか」を把握しましょう。その上で、紹介する節約術を実践して行くと良いでしょう。
結論、電気代の場合は「電力会社を乗り換える」のが最も手早く電気代節約につながりますが、乗り換える気はないという方も節約につながる方法を紹介していますので、ご安心ください。
乗り換えに興味がある方はエネチェンジから申し込むことで最大数万円のキャッシュバックがあります。
ガス代の場合は「ガス会社を乗り換える」のが最も手早くガス代節約につながります。
「とりあえずすぐに乗り換えたい」「プロに任せたい」という方は、ガス会社乗り換えをサポートしてくれる専門のサービスをすぐに利用開始する方が早いでしょう。
ガス会社乗り換えサービスの中で最大手の「ガス屋の窓口」を利用しておけば間違いないです(利用料無料)。
ちなみに、乗り換えサービスを使わずに自分で乗り換えるのはかなりハードルが高いのでおすすめしません。
電気代を安くしたい!
電気代の相場ってどれくらい?
まず、そもそも電気代の相場がどれくらいであるかを知っておくことが重要です。その上で、自分が毎月払っている電気代がどれくらい高いのかを把握しましょう。
以下、世帯人数別の平均電気料金です(全世帯平均の電気料金は一番下の行)。
| 世帯人数 | 電気代平均(2023年) |
|---|---|
| 1人 | 6,808円/月 |
| 2人 | 11,307円/月 |
| 3人 | 13,157円/月 |
| 4人 | 13,948円/月 |
| 5人 | 15,474円/月 |
| 6人 | 17,869円/月 |
| 平均 | 10,559円/月 |
※出典:政府統計の総合窓口(総務省)「家計調査_2022年」
1人暮らしの場合、平均電気料金は6,808円/月であることが分かります。2人暮らしなら11,307円/月、3人暮らしなら13,157円/月というように、世帯人数が増えるごとに電気代も高くなっていることが分かります。
ただ、3人暮らしと4人暮らしでは電気代に大きな差がないことも分かります。
電気代が高い理由
電力使用量が多い
電気代は電力使用量によって計算されているため、電力使用量が多いと当然電気代は高くなります。
では、なぜ電力使用量が多くなってしまうのか?考えられる理由を以下にまとめておきます。
・電気代がかかりやすい家電を使いすぎている
・家電の使い方が良くない
・古い家電を使っている
・ライフスタイルが変化している(家族が増えればその分電力使用量が増える)
設定されている電気料金が高い
設定されている電気料金がそもそも高い方もいると思います。その場合、電力会社の乗り換えを検討してみましょう。3万円以上の電気代節約も可能です。
電力会社に直接問い合わせてもよいですが、エネチェンジで乗り換えるとキャッシュバックなどの特典があるため利用してみると良いでしょう。
電気料金プランが適切ではない
電力会社は各々で様々な電気料金プランを提供しています。例えば、日中が仕事で家にいないなどで夜間に電気を多く使う場合、夜間の電気代が安くなるプランを選んだ方がお得です。
自分のライフスタイルに合った電気料金プランを選んで賢く節約していきましょう!
古い家電を使っている
最近の家電は省エネの性能が高いですが、古い家電は消費電力が大きいため、同じ時間使っていたとしても古い家電の方が電気代が高くなります。
例えば、10年以上前の冷蔵庫と最近の冷蔵庫で比較した場合、年間で数万円という差が出てきます。初期費用はかかるものの、新しい家電に買い替えた方がお得なことが多いです。
すぐにできる電気代節約術15選
ではここから電気代の節約術を紹介していきます。「すぐに実践できそう」と思うものから取り入れていきましょう!
1.電力会社を乗り換える
2016年4月1日以降、電力会社は自由化しており、消費者は自由に電力会社を選ぶことができるようになっています。
そのため電気代が高いと感じている方は、今の電力会社を無理に使い続ける必要はないのです。
そもそも電気料金の安い電力会社に乗り換えてしまえば、電力使用量は今まで通りでも大幅な節約が可能です。
電力会社を選ぶ上でのポイントを以下にまとめておきます。
・料金を比較する ・ライフスタイルに合った料金プランを選ぶ(日中は仕事の場合は夜間が安くなるプラン等)
・世帯人数から契約アンペア数を決める(1人暮らしなら30Aで十分)
・優良企業であるか確認する
・自分に合った支払方法ができるか確認する
また、電力会社を乗り換える場合、電力会社比較の専用サイトから申し込むことでかなりお得に乗り換えることができます。
一番おすすめの専用サイトはエネチェンジです。
直接電力会社に問い合わせをするとキャッシュバックなどは無いことが多いですが、エネチェンジから申し込みをすると、多いと「年間で3万円キャッシュバック」など大きなメリットが得られます。
2.契約プランを変更する
多くの電力会社では契約プランを複数の中から選択することができます。最もスタンダードな契約プランは「従量電灯」というプランであり、使用電力量によって電気料金が加算されるプランです。
ただ、割引が適用されるプランに変更することで安くなる場合があります。
例えば、「日中は仕事で家におらず電気をほとんど使わないが、夜はたくさん使う」という場合、夜間の電気料金が割引になるプランにすることでお得に電気を使用することが可能です。
その他にも、基本料金0円で使った分だけ支払うプランや、オール電化向けのプランなど様々なプランを提供している電力会社が多いです。
そのため、自分のライフスタイルに合った契約プランを選ぶことをオススメします。
3.契約アンペア数を下げる
契約アンペア数というのは、家庭で使用できる電流の最大量のことです。基本的に、契約アンペア数が多ければ多いほど電気料金は高くなります。
そのため、契約アンペア数を最小限に抑えることで、電気料金を節約することができます。
1人暮らしの場合は30A、家族がいる場合は40A~60Aを目安にすると良いでしょう。
電流を多く使う電化製品(電子レンジ、電気ケトル、ドライヤー等)をあまり使わない場合は、目安よりも低いアンペア数でも問題ありません。
4.電気料金の支払い方法を見直す
電気料金の支払いをクレジットカードにすることで、ポイント還元を受けることができます。
また電力会社にもよりますが、電気料金の支払いを口座振替にすることで割引が適用されるケースもあります。
契約時になんとなく支払い方法を決めてしまった方は、今一度支払い方法を見直してみると良いでしょう。
5.電気代が高くなる時間帯の使用を抑える
従量電灯などスタンダードな契約プランにしている方は時間帯による電気料金の違いはありませんが、プランによっては、時間帯による電気料金の違いがあります。
電気代が高くなる時間帯を意図的に避け、安くなる時間帯にまとめて使用することで電気代節約につながります。
例えば、昼間の電気料金が安くなるプランの場合、夜に洗濯機などを動かすのは避け、昼間にまとめて動かすほうが節約になるでしょう。
6.電力使用量を把握する
電気料金は、電力使用量によって計算されているため、普段から電力使用量の多い電化製品の使用を抑えることで、大幅な電気代節約が可能となります。
HEMS等のシステムを活用することで、電力使用量を把握することができます。把握するだけでなく、HEMSを導入することで、電化製品をスマホで遠隔操作することも可能です。
例えば、エアコンの電源を切り忘れて外出してしまった場合、外出先からスマホで電源をOFFすることが可能です。
7.省エネ家電に変える
家電全般に言えることですが、メーカーや年式によって消費電力は様々であり、消費電力の大きな家電を使っていると余分な電力を使うため電気代も高くなります。
特に、10年以上まえの冷蔵庫など、古い家電を使っている場合は要注意です。かなり損している可能性が高いです。その場合、最新の冷蔵庫に変えるだけで、年間で5,000~7,000円程度節約することができます。
「でも冷蔵庫を買う値段の方が高くつくんじゃないの?」という声もあるかと思います。
もちろん初期投資は決して安くないですが、長い目で見るとお得になることが多いです。また、最新のものに変更することで冷蔵機能もアップするため、一石二鳥と捉えることができます。
1人暮らしの場合であれば2万円程度で冷蔵庫が買えるため、年間7,000円節約できたとすると、3年でもとがとれることになります。
古い家電を使い続けている場合は思い切って買い変えてみましょう。
古い家電でなくても、いわゆる「省エネ家電」に買い替えることで電気代節約につながることが多いです。
買い替える際は、「消費電力」が今の家電よりも小さいことを必ず確認するようにしましょう。
8.自家発電する
自家発電とは、発電会社から供給される電力を使うのではなく、何らかの発電設備を用いて消費者自らが発電を行うことです。
自家発電すれば、電気を自ら生み出してそれを使うだけなので、電気代を大幅に減少させることができます。
また、自給自足でのエネルギー調達をしているため、再生可能エネルギー発電促進賦課金を抑えることができます。そして、環境問題への貢献にもなります。
さらに、自分で電気を作り出しているため、災害時の停電の心配がありません。非常用電源としても、自家発電は現在注目を集めています。
自家発電して余った電気に関しては、電力会社に売ることもできます。そう考えたら、初期の導入コストはかかるものの長期的に見ると大きな節約につながる可能性が高いです。
自家発電ってどうやれば良い?
自家発電の具体的なやり方ですが、「太陽光発電&蓄電池設置」がおすすめです。太陽光発電であれば、晴れている日であれば、ソーラーパネルが勝手に発電してくれます。
ソーラーパネルと聞くと「なんだか大きそう」とイメージされるかもしれませんが、持ち運びできる小さなものもあります。
太陽光発電をするのであれば、まずは太陽光発電の一括見積もりサービス【エコ発】などで見積をとりましょう。
蓄電池であれば、蓄電池の一括見積もりサービス【エコ発蓄電池】で見積もりをとれば間違いないです。
9.エアコン使用時なるべく外気温度に近い設定温度にする
夏はとくに冷房を長時間つかうと思いますが、その際、なるべく高い温度に設定するようにしましょう。もちろん、涼しいと感じないと意味はないですが、涼しいと感じるギリギリまでは温度を上げると電気代の節約につながります。
冷房の設定温度と外気温度との差が大きければ大きいほど電力使用量は大きくなり、その分電気代も上がってしまいます。そのため、できる限り外気温度に近い温度で冷房を使用しましょう。
ちなみに、外気温度が31℃のときに冷房の設定温度を27℃→28℃に変更するだけで、年間約940円の電気代節約になります。
ただ、無理に温度を上げて体調が悪くなってしまっては意味がないため、無理のない範囲で設定温度を調節するようにしましょう!
暖房使用時も冷房と同様で、外気温度に近い方が節約になります。
外気温度が6℃のときに暖房の設定温度を21℃→20℃に変更するだけで、年間約1,650円の電気代節約になります。
冬場は寒いため、設定温度を上げたくなる気持ちは分かりますが、目的は室内を十分に暖めることなので、室内が暖まっているならむやみに温度を上げないようにしましょう。
室内が十分に暖まってる状態であれば、設定温度を1℃変えたくらいで室内の温度はそこまで変わりません。
※出典:経済産業省 資源エネルギー庁 無理のない省エネ節約
10.電気こたつ布団使用時、掛&敷布団を併用する
こたつ布団だけを使用する際、掛布団と敷布団を併用することで体感温度が上がるため、こたつの設定温度が低めでも問題ない状態が出来上がります。その結果、電気代の節約につながります。
こたつ布団ではなく、掛布団と敷布団を併用することで、年間約1,010円の節約になります。
※出典:経済産業省 資源エネルギー庁 無理のない省エネ節約
11.断熱シートを活用する
窓に断熱シートを貼ることで、エアコンなどの電気代がかかる家電の使用時間を抑えることができます。
断熱シートは安くで手に入るため、一度検討してみると良いでしょう。
12.室外機の周りにものを置かない
室外機の近くにものを置いている場合、冷暖房の効果が弱まってしまいます。少し離れた場所に移動させるなどして、吹出し口を塞がないように注意しましょう。
13.サーキュレーターを活用する
サーキュレーターはとにかく電気代が安いです。1日8時間で1か月使用しても約180円です。
一方で、エアコンだと1日8時間で1か月使用すると、約13,000円かかってしまいます。
私自身、夏の暑い日にサーキュレーターを活用するようにしているため、大幅に電気代をカットできています。
サーキュレーターだけだと暑いと感じる場合、エアコンとサーキュレーターを併用することをおすすめします。サーキュレーターが室内の空気を素早く循環させてくれるため、エアコンの使用時間が減るはずです。
14.冷蔵庫内のものは壁から離す
冷蔵庫内のものと壁を離さないと、放熱の効率が悪くなり、余分な電力を使うことになります。
冷蔵庫内のものの上と両側が壁に接している状態から片側のみ接している状態に改善するだけで、年間約1,400円の節約になります。
※出典:経済産業省 資源エネルギー庁 無理のない省エネ節約
15.電球形LEDランプを使用する
電球交換をどうせするのであれば「電球形LEDランプ」にすることをおすすめします。明るく、寿命も長くありながら、電球形蛍光灯よりさらに消費電力が小さいのです。
白熱電球を使用している場合、電球形LEDランプに変更することで、年間約2,790円の節約になります(54W→9Wに変更した場合)。
※出典:経済産業省 資源エネルギー庁 無理のない省エネ節約
ガス代を安くしたい!
ガス代の相場ってどれくらい?
まず、そもそもガス代の相場がどれくらいであるかを知っておくことが重要です。その上で、自分が毎月払っているガス代がどれくらい高いのかを把握しましょう。
以下、世帯人数別の平均ガス料金です(全世帯平均のガス料金は一番下の行)。
| 世帯人数 | ガス代(2023年1月~3月) |
|---|---|
| 1人 | 4,430円/月 |
| 2人 | 7,628円/月 |
| 3人 | 8,650円/月 |
| 4人 | 8,208円/月 |
| 5人 | 8,413円/月 |
| 6人 | 7,646円/月 |
| 平均 | 6,723円/月 |
※出典:政府統計の総合窓口(総務省)「家計調査_2023年」 1~3月
1人暮らしの場合、平均ガス料金は4,430円/月であることが分かります。2人暮らしなら7,628円/月、3人暮らしなら8,650円/月というように、世帯人数が増えるごとにガス代も高くなっていることが分かります。
ただ、それ以降(3人以上)の世帯ではガス代に大きな差がないことも分かります。
上記のガス代相場はあくまで目安であり、「ガスの使用量」や「都市ガスとプロパンガスのどちらを使っているか」等で料金は大きく変わってきます(基本的にはプロパンガスの方が高くなります)。
そのため、以下にプロパンガス料金消費者協会が公表している都市ガスとプロパンガスの適正価格を載せておきます。
事前準備として、自宅に毎月届く検針票(最新月のものが望ましい)をご用意いただき、「基本料金」と「従量単価」をご確認ください。従量単価とは、1㎥あたりの料金のことです。
もし記載がない場合は、ガス会社と契約した際の資料に記載があります。万が一なくしてしまった場合は、ガス会社に直接「基本料金」と「従量単価」を確認してみましょう。
自分が普段支払っている料金を把握した上で、以下の適正価格と比較してみましょう。
| 都市ガス | プロパンガス | |
| 適正価格(東京ガス-プロパン換算価格) | 適正価格(協会紹介価格) | |
| 基本料金(税込) | 1,056円 | 1,650円 |
| 従量単価(税込) | 343.2円 | 308円 |
| 10㎥利用時料金(税込) | 4,488円 | 4,730円 |
適正価格よりも普段のガス料金が高い場合は、ガス料金を見直した方が良いでしょう。ガス代が高い原因と安くする方法は後で説明します。
ガス代が高い原因
ガス使用量が多い
ガス代は、ガス使用量によって算出されているため、ガス使用量が多いとガス代が高くなります。キッチンや暖房器具など、ガスを使用する機器を把握した上で使用量を見直すと良いでしょう。
では、なぜガス使用量が多くなってしまうのか?その要因を以下にまとめておきます。
・寒い時期にお湯を多く使っている(冷たい水を温めるには多くのガスを使う)
・ライフスタイルが変化している(家族が増えればその分ガス使用量が増える)
・性能の高いガス機器を使っている(性能が高いとガス使用量が多い)
設定されているガス料金が高い
契約しているガス会社が設定しているガス料金がそもそも高いということもあり得ます。ガス料金が高くなっている要因を以下に挙げます。
・ガス代値引き期間の終了(電気・ガス価格激変緩和対策事業による値引き終了)
・契約時から高い
・契約後に値上げされている
給湯器の熱効率が良くない
古い給湯器を使い続けている場合、給湯器が老朽化していて熱効率が悪くなっている可能性があります。熱効率が悪くなると、水を温めるために多くのガスを必要とします。その結果、ガス代が高くなってしまいます。
10~15年を目安にして給湯器を交換することをおすすめします。
すぐにできるガス代節約術10選
1.ガス会社を乗り換える
正直、ガス会社を乗り換えるのが一番手っ取り早くて、ガス代節約額も大きいです。
新しいガス会社に乗り換えてガス代を安くするには、自分のエリアのガス会社を比較し、一番安いガス会社と契約する必要があります。
ただ、ほとんどガス会社は料金を公表していないため、個人で会社比較することは困難です。
そのため、ガス会社乗り換えサービスを利用して、おすすめのガス会社を教えてもらい変更するという流れがスタンダードです。
おすすめのガス会社乗り換えサービス紹介
第1位:ガス屋の窓口

「どのサービスが良いか分からないという方は、ガス会社最大手の「ガス屋の窓口」が一番おすすめです。最短8営業日で乗り換えが完了するスピード感があります。さらに、紹介してもらえるガス会社は全て優良企業であるため安心して契約することができます。
また、ガス会社乗り換え後の値上げがされないように、「永久監視保証」と「一年間返金保証」が付いています。
ただし、プロパンガスしか対応していないため、注意しましょう。
第2位:エネピ
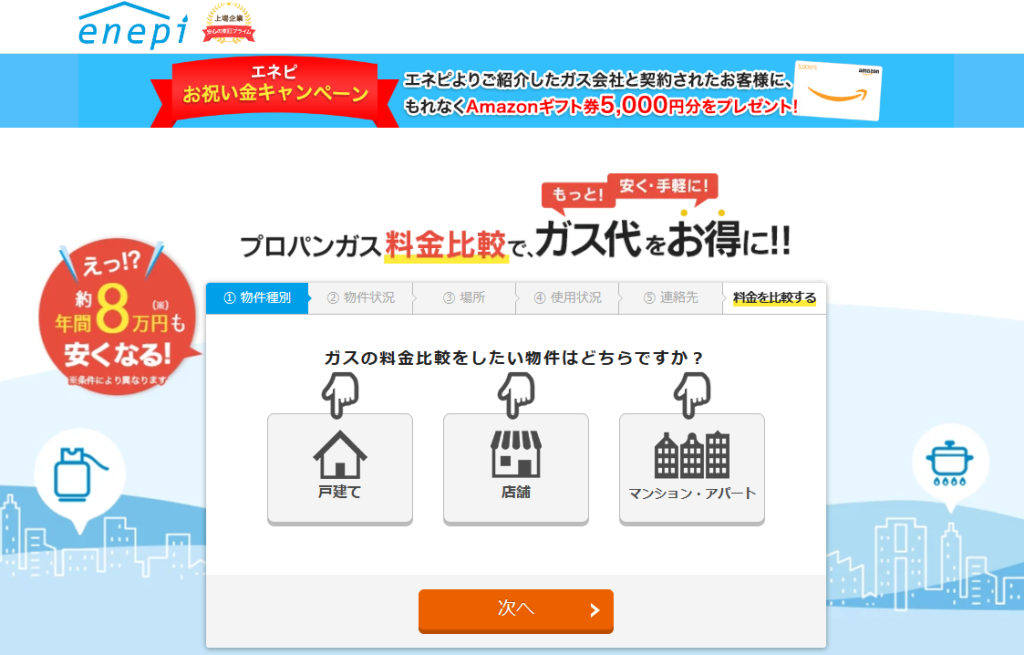
「自分でガス会社を比較したい」という方は「【エネピ】」がおすすめです。比較検討するためのガス会社情報を提供してくれるため、自分で契約するガス会社を比較して決定することができます。
第3位:ガスチョイス
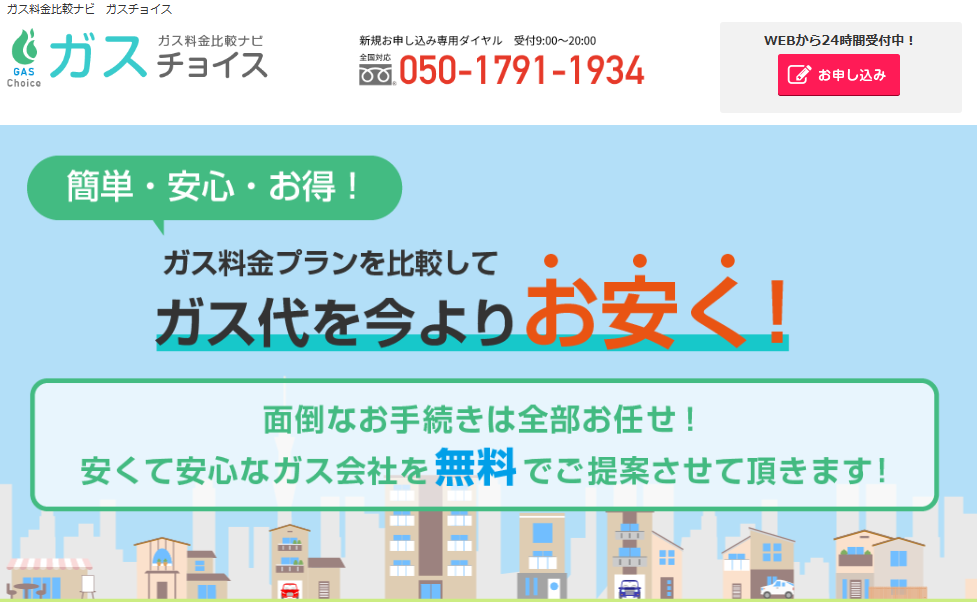
「ガス会社のことは良く分からないから丁寧にスタッフに教えてほしい」という方は【ガスチョイス】がおすすめです。
ガスチョイス運営会社の親会社である「株式会社Wiz」はコールセンター業の経験と実績が豊富であるため、電話対応スタッフの対応が良いです。
ただ、「ガス屋の窓口」や「【エネピ】」のように料金監視保証制度がありませんので、注意しましょう。
2.ガス使用量を抑える
ガス使用量を抑えればガス代は安くなります。ガス会社乗り換えが難しい場合は、使用量を見直すことも考えていきましょう。
ただ、ガスはキッチンや暖房器具など生活する上で必要なアイテムに使われています。そのため、ガス使用量を抑えることで生活が不自由になってしまっては本末転倒です。
不自由にならない程度、かつすぐにできるガス代節約術7選を後で紹介します。
3.ガス代を値下げしてもらう
ガス会社乗り換えが難しい場合は、今のガス会社に値下げ交渉してみるのも良いでしょう。ガス会社によりますが、上手くいけば大きな節約になることがあります。
私自身、実際にガス料金が高いことに悩んでいたため、自分でガス会社に電話し、「料金を下げてほしい」と伝えたところ、年間で約3万円の節約につながりました。
特にプロパンガスの場合、自由料金であるため、プロパンガス業者が好きなように価格を決めることができます。
その結果、適正価格よりもはるかに高い料金設定がされていることもあります。そのことをガス会社も自覚しているため、値下げ交渉されたら案外スムーズに値下げに応じてくれることもあります。
高いと感じた段階で、まずはガス会社に連絡してみることをおすすめします。
すぐにできるガス代節約術を紹介します。ぜひご自身の生活に取り入れて、ガス代を少しでも安くしていきましょう。
4.給湯器の温度は低めに設定する
普段手を洗うときや食器洗いの際に、温かいお湯を使っていないでしょうか?
給湯器の温度が高ければ高いほど、多くのガスを必要とするため、ガス代は高くなります。冷たい水を使いましょうというわけではありませんが、設定温度を38℃程度にするなど、低めに設定しておきましょう。
ただ、そのままの水を使うのが最も節約にはなるため、夏場などは水で洗うのも良いでしょう。
5.お風呂の追い炊き回数を減らす
お子さんが多い家族など、世帯人数が多い場合、お風呂に入るタイミングが全員バラバラだと追い炊き回数が増えてしまいます。水を温めるためにはガスが必要なため、その回数が増えればその分ガス代も高くなります。
一日に追い炊き回数を1回に抑えた場合、年間で約6,190円の節約になります。
「同じタイミングでお風呂に入る」「浴槽に蓋をして温度低下を防ぐ」などが有効でしょう。浴槽に浸かっているときは半分だけ蓋をするとお湯の温度低下につながります。
フタが邪魔と感じる場合、「保温シート」を使うという手もあります。
※出典:経済産業省 資源エネルギー庁 無理のない省エネ節約
6.電子レンジを活用する
短時間(数分程度)の過熱料理であれば、ガスコンロではなく電子レンジを使った方がガス代節約になります。ただ、長時間の場合に電子レンジを使うと、電気代が高くなってしまうため、調理方法によって使い分けるのが良いでしょう。
野菜を調理する際、ガスコンロではなく電子レンジを活用すると、年間で最大約1,000円の節約になります。
※出典:経済産業省 資源エネルギー庁 無理のない省エネ節約
7.料理で強火を使わない
ガスコンロで調理する場合、強火よりも中火などにした方がガス使用量が減り、年間約390円の節約になります。特に「炎がなべ底からはみ出さない」ことが大事です。
8.食器洗い乾燥機を活用する
食器洗い乾燥機を活用することで、ガス代節約につながります。電気代はかかりますが、食器洗い乾燥機でまとめ洗いをすることで年間約19,090円の節約になります。
※出典:経済産業省 資源エネルギー庁 無理のない省エネ節約
9.給湯器の熱効率を上げる
古い給湯器を使い続けている場合、老朽化等により熱効率が下がっていて余分にガス代がかかっていることがあります。新しいものに変えるなどして熱効率を上げることでガス代節約につながります。
10.なるべく電気ケトルでお湯を沸かす
電気ケトルがある場合は、ガスコンロではなく、なるべく電気ケトルでお湯を沸かすようにしましょう。電気代はかかりますが、1回お湯を沸かすのに約3.26円で済むためかなり節約になります。
水道代を安くしたい!
水道代の相場ってどれくらい?
まず、そもそも水道代の相場がどれくらいであるかを知っておくことが重要です。その上で、自分が毎月払っている水道代がどれくらい高いのかを把握しましょう。
以下、世帯人数別の平均水道料金です(全世帯平均のガス料金は一番下の行)。
| 世帯人数 | 上下水道代(2023年1月~3月) |
|---|---|
| 1人 | 2,163円/月 |
| 2人 | 4,258円/月 |
| 3人 | 5,433円/月 |
| 4人 | 6,260円/月 |
| 5人 | 7,377円/月 |
| 6人 | 9,998円/月 |
| 平均 | 4,111円/月 |
※出典:政府統計の総合窓口(総務省)「家計調査_2023年」 1~3月
1人暮らしの場合、平均水道料金は2,163円/月であることが分かります。2人暮らしなら4,258円/月、3人暮らしなら5,433円/月というように、世帯人数が増えるごとに水道代も高くなっていることが分かります。
水道代が高い原因
水の使用量が多い
単純に水をたくさん使っていることが考えられます。
例えば、「在宅勤務が増えて家で水道を使う機会が増えた」「子供が産まれて家族が増えた」などライフスタイルや家族構成が変わると、今までよりも水道をたくさん使うこともあります。
また、「水栓から水漏れしている」ということも考えられます。
蛇口からポタポタと水が漏れていないかチェックしてみましょう。もし漏れているようであれば、早めに業者に直してもらいましょう。
検針できていない
毎回の検針のタイミングで検針担当者が検針した結果をもとに水道料金は決まっています。
ただ、その検針がきちんとできていないと、水道料金が余分に高くなっているなんてこともあります。「そこまで水を使っていないのに不自然に高いなあ」と感じる場合は一度管理会社へ連絡してみましょう。
水道メーターが故障している
計量法によって、8年経つと水道メーターを交換することが義務付けられていますが、ごく稀に水道メーターが故障していることがあります。
こちらも、異常に水道料金が高いと感じる場合は管理会社に連絡してみましょう。
そもそも水道料金が高い
今使っている水道管は、多くの場合かなり昔に敷設されています。そのため、水道管の老朽化に伴い更新が必要となっています。
したがって、予算不足が発生し、やむを得ず水道料金を値上げする自治体が増えています。水道料金が値上げされる場合、必ずチラシやインターネット等で通知が来ますので、一度確認しておきましょう。
すぐにできる水道代節約術5選
1.食器洗い乾燥機を活用する
食器洗いをする際、手洗いだと年間で約25,560円の水道代となります。ただ、食器洗い乾燥機を活用すると年間で約19,090円に抑えることができます。
したがって、食器洗い乾燥機を活用することで年間約6,470円の水道代節約につながります。
また、食器洗い乾燥機であれば、食器を入れて放置するだけで済むため、家事の負担も軽くなるというメリットがありますね。
※出典:経済産業省 資源エネルギー庁 無理のない省エネ節約
2.洗濯機を使うときはまとめ洗いする
洗濯機を使う際、まとめ洗いをして洗濯機を回す回数を減らすことで水道代を節約することができます。
洗濯機の定格容量に対して4割の分量の洗濯物を入れて洗濯する場合と、8割にして洗濯機を回す回数を半分にした場合を比較した場合、後者の方が年間約4,360円の水道代節約につながります。
※出典:経済産業省 資源エネルギー庁 無理のない省エネ節約
3.シャワーを出しっぱなしにしない
シャワーからお湯を出しっぱなしすると、水道代だけでなくガス代も高くなります。シャワーを1分間出しっぱなしにすると約12Lの水が無駄になっています。
反対に、45℃のお湯を流す時間を1分間短縮するだけで年間約1,140円の水道代節約につながります。
使わないときはこまめに止めることで節約を実現していきましょう。
4.湯舟に浸かる
家族が多い場合、シャワーよりも湯舟にお湯を張って追加回す方が水道代の節約になります。
その際、追い炊き回数が増えてしまうとガス代が高くなってしまうため、なるべく立て続けにお風呂に入る工夫ができると良いでしょう。
5.節水シャワーヘッドを活用する
シャワーヘッドの穴の数や大きさが調節されている節水シャワーヘッドに変えることで、水道代を節約することができます。
節水量の多いものだと、50%の節水も可能になります。
まとめ
光熱費(電気・ガス・水道)の節約方法を解説してきました。これらをほぼ全て実践すれば年間で数万円の節約も可能です。実際に、私は年間7万円の光熱費節約に成功しています。
当サイトでは、「電気」「ガス」をメインに取り上げており、「電気代」「ガス代」に特化した節約術も以下の記事で紹介していますので、そちらもぜひご覧ください(もっと多くの節約術を紹介しています)。




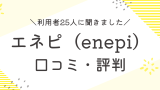

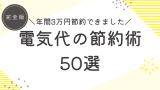



コメント